JOURNAL
届かぬ場所–
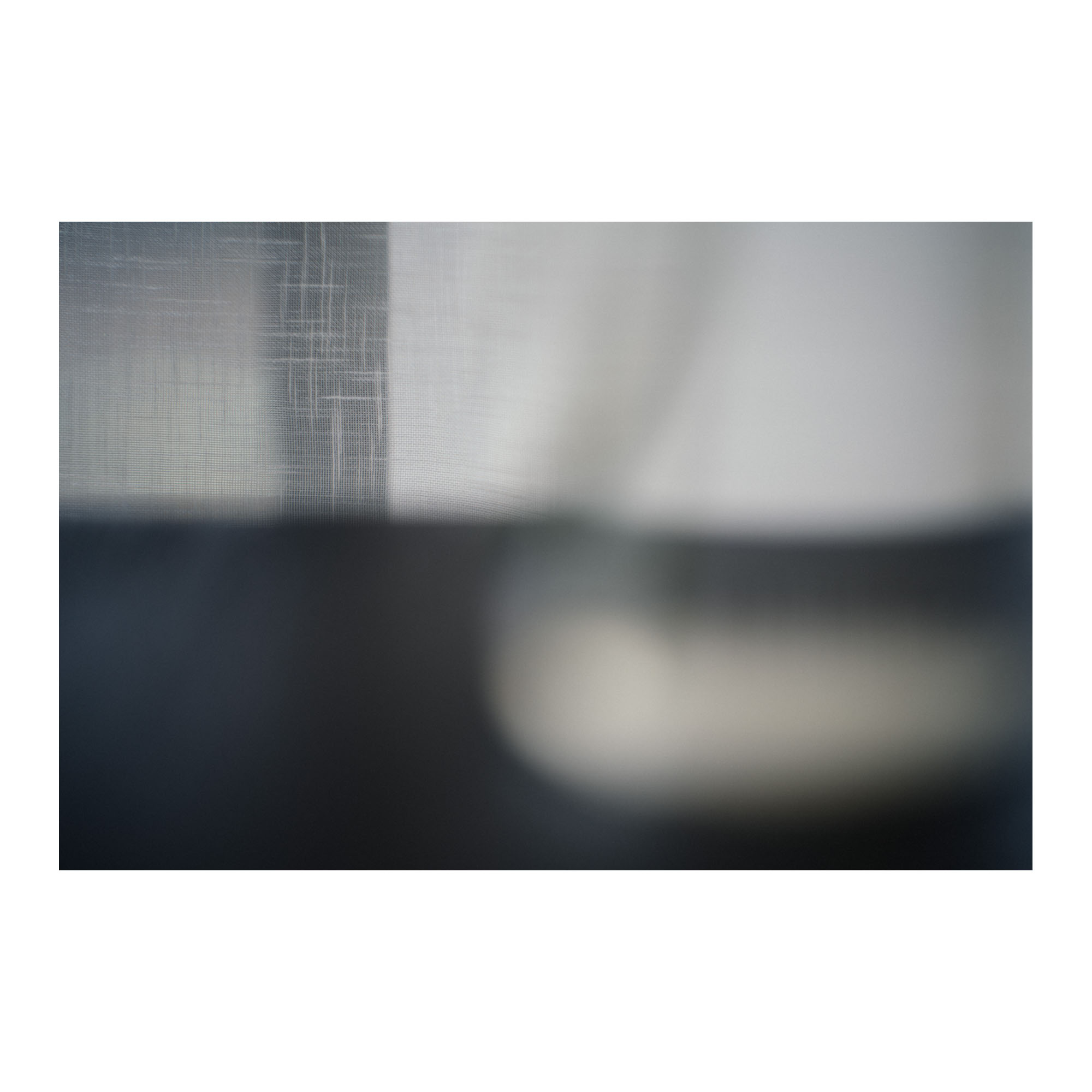
沈黙の中に言葉が立ち現れれば、それはもう詩となっている、とマラルメはいう。マラルメにおける詩は言葉を超えた無に至る旅であった。
ただし完全な沈黙は何も分節しない。禅において、また公案では絶対無分節と経験的分節の同時現成が核であり、この経験的世界(ロゴス)の否定、つまり論理が記録する文化的表象としてのリアリティを剥奪するのが第一に求められる。
マラルメは意味それ自体ではなく、意味の余韻を詩の境地とした。それは言語が立ち現れる前の純粋有を無媒介的に何とか言語で言い表そうとする矛盾の発露でもある。
「言葉が届かないところに詩がある」
このマラルメの言葉を拡張してみる。
「意識が届かないところに存在がある」
「存在」は「世界」に変えても良いだろう。
マラルメは今や言葉を発することができず、さぞ幸せなのだろうか。